おばあが縁側で「ぜんまい」を干していた。
新聞紙を敷いて、その上に丁寧に並べて、
夕方になると、ひとつひとつ向きを変える。
特別な言葉はなかったけれど、
その背中には、何か伝わってくるものがあった。
うちの親父は、僕が小さい頃に亡くなった。
おふくろは、朝から晩まで働き詰めだった。
おばあは、そんな僕らの暮らしに、
そっと手間を注ぎ続けてくれた。
孫が熱を出したと聞けば、
大雪の日でも自転車で
駆けつけてくれるような人だった。
自分の人生は、決して楽じゃなかったはずなのに、
それを誰かのせいにすることもなく、
いつも嬉しそうに、僕たち孫を褒めてくれた。
そんなおばあが作ってくれた、
干したぜんまいと、油あげと、しらたきの炒め物。
たぶん、使っていたのは市販のサラダ油。
特別な調味料があったわけでもない。
でもその料理は、いつも大鍋で作るのに、
僕ひとりで平らげてしまうほど、
何よりのごちそうで、本当に美味しかった。
少し甘じょっぱくて、
ふわっと自然の香りがして、
口の中に“暮らし”の匂いが広がった。
「うんめけ?(美味しいかい?)」
「いっぺけ(いっぱい食べな)」
いつもそう言ってくれるおばあの口癖。
あの香りと味は、今でもふと思い出す。
なつかしさというより、
その一皿に宿っていたのは、
きっと「心」だった。
言葉じゃなく、感覚で残る記憶。
「何かをしてくれた」ことよりも、
「何かをし続けていた」背中のほうが、
ずっと深く、僕の心に染みていた。
料理も、掃除も、草取りも──
おばあにとっては全部が“暮らしそのもの”だった。
そこにはいつも、
祈るような丁寧さがあった。
でも、手間って、
愛情そのものではないと思う。
時間をかけることが、
必ずしも手間ではないように。
“心がここに在る”ということ。
どんなに忙しくても、
その瞬間だけは、
目の前のものを丁寧に扱う。
それが、手作りとか、出来合いのものとか、
そういうことじゃない。
子どもはきっと──
その一瞬の”手間”を
親や祖父母の“心”を感じながら食べている。
僕は、それを身をもって知っている。
そして、これを読んでくれているあなたも、
きっと知っているはず。
あのレシピ、訊いておけばよかったな。
もう二度と食べることはできない。
もちろん特別な作り方をしてなんていないだろう。
でも、あの味があったから、
僕は今でも「どう生きたいか」を思い出せる。
僕は、きっと“ばあちゃん子”だった。
忙しかったおふくろに代わって、
静かに、そばにいてくれた人。
言葉より、手間。
教えより、暮らしの背中。
おばあの存在が、
今も僕の輪郭をやさしく縁取ってくれている。
だから僕も──
誰かの輪郭をやさしく縁取るような
そんな人でありたいと思う。
──あなたの暮らしの中には、
どんな“記憶の手間”がありますか?
そして、どんな香りや味が、
あなたの原点を思い出させてくれますか?
生き方の見本になるものが、
きっとあなたの記憶のどこかにもある。
僕は、あの日、すでに受け取っていたんだね。
今日も一日、おつかれさま。
ふとした香りや日常の記憶が、
あなたの心をやわらかく包んでくれますように。
── Atsushi
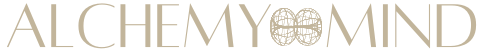

コメント